年を重ねるにつれて、「骨折をしない」ということは健康寿命を延ばすために重要なポイントになってきます。
一度骨折してしまうと、療養の間に全身の筋肉が落ちてしまったり、ひどい場合は要介護状態になってしまうため、日常生活を送るうえで大きな支障になってしまいます。
しかし糖尿病を患っている場合は、骨密度が低くないにもかかわらず骨粗鬆症になり、骨折してしまうリスクが高いと言われています。
これはなぜ、どのようなメカニズムでそうなってしまうのか、また骨粗鬆症を予防するための方法について解説します。
骨粗鬆症とはどんな病気?チェックのポイントは?
骨粗鬆症とは、一言で言うと「骨がもろくなって骨折しやすくなる病気」です。
一般的には女性に起こりやすく、閉経によって女性ホルモンの分泌が低下すると、骨密度が低下し発症に至るというケースが多いですが、もちろん女性だけの病気というわけではなく、栄養・運動不足などの原因から男性が発症することもあります。
骨粗鬆症の診断にあたっては、
・これまでの骨折歴
などを参考にします。
骨密度は肉眼ではもちろん分からないため、エックス線を使って測定を行います。
専用の装置を使うことで、骨密度を正確に把握できるほか、気づきづらい部分の骨折なども発見することができます。
※実は背骨の骨折(椎体骨折)は傷みが感じられず気づかないという場合があり、エックス線検査で初めて分かったということも珍しくありません
とはいえ、エックス線の検査は基本的に病院に行かなければできません。
骨粗鬆症の兆候がないのに検査に行くなんて・・・と思っている方は、次のチェックポイントを確認してみましょう。
・腰や背中に慢性的な痛みがある
・親(実親)のうち1人以上が、大腿骨もしくはその付近を骨折したことがある
・背中を壁につけて直立した時に、後頭部が壁につかない
この中で1つでも当てはまる場合は、骨粗鬆症の可能性があるので検査を受けることをおすすめします。
糖尿病が骨粗鬆症の原因となるのはなぜ?

糖尿病と骨粗鬆症ってどんな関係があるの?
骨粗鬆症は糖尿病の合併症の1つと言われるくらい、密接な関連があります。
通常は、何らかの原因により骨密度が低下し、骨がスカスカになると骨折しやすくなる(=骨粗鬆症になる)のですが、糖尿病を患っている場合は骨密度がそれほど低くなくても、骨折しやすくなることがあるのです。
これには主に2つの原因があると言われており、実際の研究結果でも、糖尿病を患っている方は通常の骨粗鬆症患者より骨密度が少し高くても、骨粗鬆症を発症するリスクが高いことが報告されています。
骨の強度を支えるコラーゲン架橋の質が低下する
骨の強度は、蓄積されたカルシウムと、それらをつなぎ合わせて支えるコラーゲン架橋の2つによって成り立ちます。
ところが糖尿病を患っている場合、コラーゲン架橋に糖化たんぱく質が蓄積することで質が低下し、骨折しやすくなってしまうことが知られています。
実は骨密度の測定ではコラーゲン架橋の劣化を検出することができないため、骨密度が少々高くても骨折しやすいという状態になってしまうのです。
骨の修復が遅くなる
体中の他の細胞と同様、骨も古くなると順次新しいものへと作り替えられていますが、糖尿病を患っている場合は骨の新陳代謝が遅く、骨の修復が遅くなってしまいます。
このことも、糖尿病患者の方が骨折しやすくなる原因の1つとして考えられています。
骨粗鬆症を予防するには
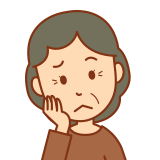
骨粗鬆症を防ぐためにはどうしたらいいの?
骨粗鬆症や骨折を防ぐために重要なポイントは次の2点です。
・骨折を防ぐ体づくり・環境づくり
栄養・運動療法によって骨の強度を上げる
骨を強くする、骨密度を上げるために必要な栄養素が「カルシウム」と「ビタミンD」です。
骨密度はある一定の年を超えると年々低下していってしまいますが、これらの栄養素を摂ることでできるだけ骨密度の低下を遅くすることが必要です。
牛乳や小魚など、カルシウムが豊富な食品を積極的に食事に取り入れ、1日に必要なカルシウム量(700~800mg)を確保しましょう。
またビタミンDはさんまや鮭、かれいなどの魚や、干しシイタケなどに多く含まれています。
これらの食品からの摂取のほか、ビタミンDについては体に日光を浴びることでも生産できるので、屋外での運動もおすすめです。
骨を強くするにはある程度運動によって負荷をかけることが必要なので、晴れた日のウォーキングなどはビタミンD生産と骨への負荷とが両方でき一石二鳥です。
骨折を防ぐ体づくり・環境づくり
骨の強化だけでなく、体全体の筋肉やバランス感覚を鍛えることで転倒しづらくなり、骨折を防ぐことができます。
毎日でなくても構わないので、週に数回でも筋力トレーニングやバランス強化のための運動を行ってください。
急に激しい運動をすると逆効果ですので、まずは体を傷めない負荷・回数から始め、徐々に強度を上げていくようにしましょう。
また骨折になりやすい環境や状況を避けることも対策として重要です。
例えば家の段差を解消する・スロープをつけるといった対策や、足元が見えやすいよう明かりを増やすなどの対策が考えられます。
また慌てて/滑って転ぶことがないよう、
・フローリングの上にカーペットなどを敷く
なども事前にできる対策と言えるでしょう。
糖尿病が骨粗鬆症を引き起こすメカニズムまとめ
改めて、糖尿病が骨粗鬆症を引き起こすメカニズムをまとめると、糖尿病により
・骨の修復が遅くなる
といった状態になることから、骨粗鬆症(=骨折しやすい状態)を発症します。
糖尿病を患っている方は、少々骨密度が高くても安心せず、骨折しづらい環境や体の状態を作りましょう。
一度骨折になってしまうと、治療や療養によって運動に制限がかかり、さらに骨粗鬆症が加速しますので、まずは最初の骨折を起こさないことが肝心です!



コメント